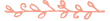今回は、番組制作のあずさです!
隊員になる前は映像制作や写真撮影の
仕事をしていたというあずさ君。
フリーランスだったので、報道、企業紹介、
記録撮影など様々で、
担務も記者・ディレクターのときもあれば、
撮影など技術担当のときもあり
幅広くオファーを受けていたそうです。
『放送作家しかやらん!!』という私とは大違いの
マルチプレーヤーです。素晴らしい!
現在は、トンガで活動中!
それでは、いってみましょ〜〜〜!
*現在、どんな活動をしていますか?
トンガの首都にある国立放送局で活動しています。コンテンツ制作全般に携わっていて、局として現在注力しているインターネット向けの写真撮影が中心の一つになっています。番組は主にトンガ語で放送されていて、編集に携わるのは難しいこともあり、映像撮影や録音、配信などを中心に支援しています。
日本のメディアとの違いとしては、配属先には番組表が存在しません。収録時間が伸びたら放送時刻もそれに応じて変動してしまうためです。チャンネル数が非常に少ないこともあって、テレビ放送自体があまり重視されていないのが現状です。
*どんなお部屋に住んでいますか?
普段は一軒家に一人暮らしです。諸事情あって引っ越して、今は快適な家に住ませてもらっています。誰も来ないゲストルームは仕事部屋&機材庫として活用しています。なお、このDiaryを書いている10月現在は1か月間の出張中で、ハアパイ諸島という離島で同僚と共同生活をしています。島内で一番栄えている地域ですが、牛や馬が家の前を散歩している牧歌的な場所です。
*派遣国で一番驚いたことは?
各家庭の犬がきちんと番犬をしていること。多くの家が犬を複数飼っていて、フェンスの無い家の前を通ると、道路脇を歩いているだけで犬が追いかけてきます。身に危険を感じるので、棒や石で追い払うのが日常になっています。JICAボランティアは交通安全の観点で自動車の運転が認められていませんが、徒歩や自転車移動で犬に噛まれる不安のほうが強いです。
*これまでの活動で一番うれしかったことは?
撮影した写真の出来が良かったようで、王室から指名を受けて王室行事の公式撮影を担当したこと。
*活動中の失敗や苦労していることは?
日常の活動は英語でほぼ問題ないのですが、番組はトンガ人の母語であるトンガ語で放送されています。言語の問題で、編集や構成について支援が出来ないのは悔しいところです。ただ、トンガ語を覚えてその支援を目指すよりも、英語で出来る支援に集中するほうが実効性は高いと割り切って考えています。また、撮影など実務のワークショップを始めましたが、伝えた内容を定着させるためにどのような手法を採るべきか考え中です。(誰かアドバイスください)
*最近買った一番高いものはなに?
トンガの民族衣装で正装となるタオバラとカファ。洗えると聞いて洗ってみたらボロボロになってしまったので新たに買いました。
*今、一番欲しいものは?
ユニクロの洗濯できるジャケット。日本から持参して、活動に便利で気に入っていましたが、預かるよと撮影中に同僚から言われて預けたら紛失されました…。皆さんお気をつけください(泣)
*2年間でやりたいこと&これからの目標は?
番組制作の実務では、問題なく放送出来たり出来なかったり…という状態を抜け出せるように、基礎的な技術の定着やルールの策定と、属人的な状態の脱却を目指しています。また、番組自体の制作力向上を目指すだけでなく、番組編成を工夫したり、営業との連携を強めたりして、情報源としても広告としても映像メディアの価値が高まるように活動していきたいと考えています。
社会の礎ともいえるメディアへの支援を通じて、トンガの社会に少しでも貢献していきたいです。
*みんなにメッセージをお願いします!
同期のみんなに:活動も残り1年半となります。帰国してからのことも考え出さないと、と思い始めています。いろいろ話聞かせてください~。
【あとがき from non】
Yeaaaaaaaaaaaaah!駒ヶ根の「チームMedia」ですよ!!私たちの隊次は謎にメディア隊員が多くて番組制作・ジャーナリズムで4人もいました。(一人もいないことがほとんどらしいのに…)ちゃんとボリビアにメディアTシャツ持ってきて、仕事で着てるよ〜(あれ、丈夫よね)!いやしかし、場所が違えばメディアの様式も違う、立場もやり方も常識も違うというのを私たちは身をもって実感している最中で。実感できる貴重な機会が得られたことに感謝する一方で、渦中にいるからこそ「いや、これどうしたらいいのよ…」の連続でもあるよね。同期のメディア隊員が世界のあちこちで頑張っているのをみると(たまに稼働するグループLINE笑)、私ももっと頑張ろうって思える!王室ご指名&密着取材、すごいなぁ。あずさ君、いつもいい刺激をありがとう!!帰国後は…きっとなんとかなるよ!!

あずさ、ありがとうございました。
ということで、次回は誰かな〜〜!?
non。